「オンラインGDって、正直どう進めたらいいか分からない…」
そんな不安を抱えていませんか?
27卒の就活では、オンライン面接に加えてオンラインGD(グループディスカッション)の導入がますます増えています。
ライボ(Job総研)が2022年卒の学生を対象に実施した調査では、93.0%の学生が就職活動のオンライン化に賛成と回答しています。
また、HR総研とONE CAREERの調査では、対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型の選考形式を希望する学生が多数を占めており、企業側もこれに対応した採用活動を行う時代となっています。
本記事では、「オンラインGD コツ」「オンラインGD ファシリテーター」「27卒 オンライン選考」など、就活生が抱える疑問をまるごと解決していきます。
オンラインGDとは? 対面との違いとは

オンラインGD(グループディスカッション)とは、ZoomやGoogle Meetを通じて複数人で議論を交わし、課題に対して結論を導く形式の選考です。
人数は4〜6人、制限時間は20〜30分が主流。
一番の違いは、「空気感が伝わりにくいこと」。
頷きや目配せといった非言語コミュニケーションが使いづらく、一人で話して一人で完結になりがちです。
だからこそ、オンラインGDでは「発言の明確さ」「役割分担」「タイムマネジメント」がより重要になります。
27卒が通過率を上げる評価ポイントはここ!

就活生の多くが「意見を言えば評価される」と思いがちですが、実はそれだけでは不十分です。企業が見ているのは、以下のようなポイントです。
① 論理の筋が通っているか
発言に根拠があり、他の人の意見と比較・調整できているかが見られます。
② 協調性を持っているか
“我が強すぎる人”や“空気を読まない発言”は減点対象。周囲との連携力がカギ。
③ オンライン特有の配慮ができているか
話す順番を整理したり、マイクのオンオフを調整するなど、進行全体に気を配れるかも評価されます。
ファシリテーターが有利? 役割分担のコツ
オンラインGDでは役割を担うことで発言機会を増やせるため、消極的になりがちな人ほど「役割を取る」戦略が効果的です。
ファシリテーター(進行)
会話の流れを整えるポジションです。
オンラインでは「順番を明確に振る」「テーマをチャットで共有」など、細やかな気配りが好印象に直結します。
例:「では〇〇さん→△△さんの順でお願いします」
書記(メモ・共有)
議論の内容をWordやGoogleドキュメントに記録し、画面共有で全員に見えるようにします。
「書いて整理する」ことが議論の可視化になり、面接官にも貢献度が伝わりやすい役割です。
タイムキーパー
残り時間を管理し、「あと5分です」「結論の時間に入りましょう」といった時間配分の声かけが中心。
オンラインでは、チャットで静かに知らせる工夫も効果的です。
議論を回す型を覚えておこう
オンラインGDでよく起こるのが、「話が脱線する」「議論がまとまらない」という展開です。
原因の多くは、参加者全員がなんとなく話し始めて、ゴールが共有されていないこと。
特にオンラインでは、空気の変化や圧が伝わりづらく、全員が正しいことを言ってるのに、話がかみ合わないということが頻発します。
そんなときこそ、頼りになるのが5ステップのフレームです。
ステップ1|課題の再確認(テーマの解釈)
与えられたテーマをそのまま話し始めるのは危険です。
まずは「このテーマってどういう意味?」を全員で確認します。
例:「”地方創生を促進するには”というテーマは、地方に人を呼ぶこと? 地元企業の活性化?」など、共通の理解を持つことが出発点です。
ステップ2|アイデア出し(質より量でOK)
次に「とにかく出す」フェーズ。ここでは否定をせず、どんな意見も拾います。
オンラインでは、チャットやGoogleドキュメントにアイデアをメモして視覚的に共有するとスムーズです。
ステップ3|評価軸の設定(どう比べる?)
複数のアイデアが出たら、「何を基準に良し悪しを判断するか」を決めます。
例:実現可能性・コスト・インパクト・継続性など。評価軸があることで、次の絞り込みがロジカルになります。
ステップ4|比較・絞り込み
アイデアを評価軸で比べて、2〜3案に絞ります。このときも一人で判断しないことが重要。
「私たちの議論の中では、AとCが現実的に見えるね」といった合意形成がポイントです。
ステップ5|結論と理由の整理
最後は結論を決め、なぜその案になったのかを理由とセットでまとめます。
ここが抜けると、面接官に「なんとなく決めたな」と映ってしまうので要注意。
この型を頭に入れておけば、ファシリテーターでなくても「今、ちょっと論点がズレてるかも」などと軌道修正ができ、議論を立て直せる人として一目置かれる存在になれます。
オンラインGDの“映える”振る舞いとは?
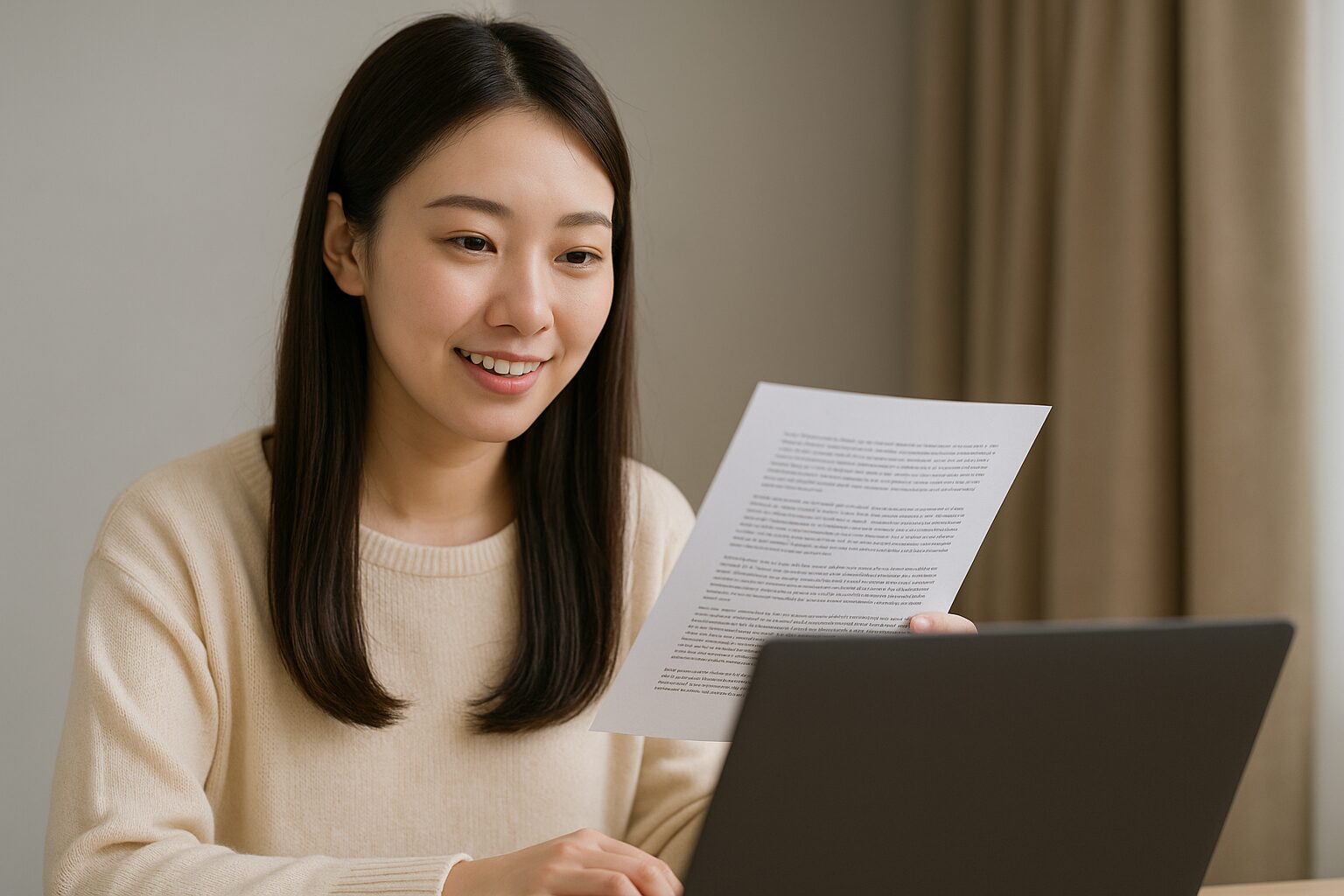
実は、通過率に大きく関わるのが非言語コミュニケーションです。
オンラインでは空気を読みにくいからこそ、表情やリアクションがより大切になります。
視線は「カメラ」へ向ける
人の顔ばかり見ていると、うつむき気味になってしまい、暗く映ることがあります。
「今、自分が誰に話しているか」を意識し、発言中はカメラを見るクセをつけましょう。最初はぎこちなくても大丈夫、練習で自然になります。
頷き・表情で安心感を与える
自分が話していないときも、適度に頷いたり、口角を上げて聞く姿勢が大切です。
これがあると、他の参加者も話しやすくなり、結果として全体の議論が活発化する=あなたの評価も上がるという好循環が生まれます。
発言の終わりに「どう思う?」とパスをつなぐ
例えば、「私はA案がいいと思います。〇〇さんはどうですか?」と次に振ることで、議論にリズムが生まれます。
この“パス回し”ができる人は、進行力と気配りができる人材として高く評価されます。
まとめ:27卒が今すぐやるべき3つのこと
Zoom・Google Meetでの発言練習を始める
ファシリ・書記の練習を一度でも経験しておく
過去問(ONE CAREERなど)を参考に想定テーマを考えておく
オンラインGDは“慣れ”がすべてです。対策次第で結果は大きく変わります。
27卒の皆さん、今この時期からWebテスト対策や面接準備を始めて、自分らしさが伝わるGD対策を進めていきましょう!



コメント